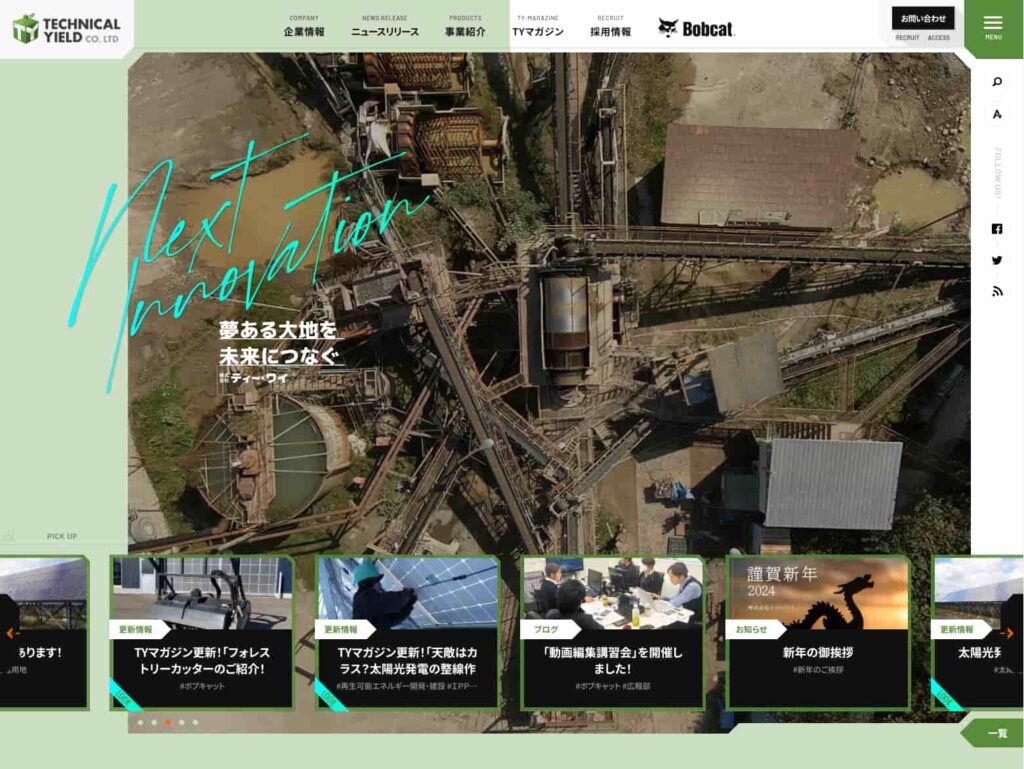― この5~6年で次々と新規事業を始められて、社員数も増えたと伺っています。どのようなお仕事で、どのような方々がいらっしゃるのですか。
弊社はもともと、公共土木工事を主とする株式会社山内組(北海道河西郡)から産廃事業を切り離す形で設立して約30年になるのですが、2014年から新規事業を増やし、再生可能エネルギーの開発・建設、土木資材の販売、重機の販売と整備、ITなど事業は多岐にわたります。メンバーも様々で、新卒採用からの20代前半、ベテランの50〜60代、そして新規事業の即戦力として中途採用した30~40代が中心となっています。中途採用組は、例えばディーラーの店長から営業になった人もいれば、鉄工所で電気関係の技術者だった人が再生エネルギーの発電所の仕事をしているなど、専門知識に加えて、他にも得意なことがあり、経験を地続きに生かしている。そんなメンバーが揃っています。管理職経験者はもちろん、採用面接をする立場だった人もいます。
― そういった方達と、若手の方で、一緒にトレニアを使ってくださっているんですね。
まず若手に関しては、2日間の外部の研修に行ってもらう他は、基本的には働きながら覚えていくスタイルなので、一般的な社会常識について、何らかの方法で研修を行う必要があると思っていました。では若手だけで良いのかというと、上の人たちとの「溝を埋めたい」という想いがあったんです。大きな溝ではないのですが、ベテランになると経験からの感覚を優先したり、マイルールができていることがあります。経験を生かしてフォローし合えるという良さがある一方で、会社としてスタンダードを定める難しさも感じていました。さらに、40代と20代の世代ギャップもあります。週6日、上からのプレッシャーの中で働いてきた世代と今の20代では、例えばブラック、ホワイトといった言葉の意味合いも変わってきます。実際にいまトレニアの回答を見ても、若手は厳しめのメッセージに対して「(社会で働くということは)そんなに厳しいんだな」と感じている傾向があります。そういった溝を埋めるというか、価値基準を揃えたいと感じていました。もちろん、既にしっかりできている人もいるのですが、誰がやる、やらないと分けてしまうと、疎外感が生まれてしまいますので、みんなでやることにしました。
― 共通の価値基準がないために、問題が起きることはありましたか?
時々ありました。例えば上司が部下に「こうだ」と言い切ってしまって、それはある面で間違いではないのですが、会社としてスタンダードにできるかというと難しいところもあって、後から会社として言い直してもらわなくてはいけなかったり。こういうことがあると、みんなが辛い思いをするし、その後の関係性にも影響が出てしまうので、心苦しく思っていました。また、共通の価値基準がないと、誰の言うことは良い、誰の考え方は良くないなど個人の話にもなりがちです。仕事をしていればトラブルや問題に当たることは必ずあるので、そのときに偏った考えを持ってしまうと、最終的に損をするのは本人です。自分の考えと合わないときでも、会社や誰かが悪いと思考を止めてしまうのではなく、こうしてみたらどうだろう、やってみたらどうだった、そう考えられるほうが社会人として健全ですよね。みんなで共通認識を持って、会社としても正しい声は受け止めて改善していく。そういう環境にしていく必要を感じていました。トレニアにはその「共通認識」を育ててくれる役割を期待しました。
― 1ヶ月のお試し導入は、慎重に、幹部のお二人だけでやっていただきました。
「厳しいクイズ」だと聞いていたので、慎重に、幹部だけでやりました(笑)。実際にやってみると、厳しいものは厳しい、でも「これくらいの厳しさは受け止めないと、どこにいっても働けないよね」と、非常に共感できて、こうした意識の下地があれば働くことの助けになると感じました。やることとしては、クイズが出て、答えて、振り返るだけなので、これくらい簡単なら続けられそうだと。会社の状況に合わせて、どう活用するか自由に考えていけるなと感じました。
― 導入時には、「共通認識を育てる」というメッセージを伝えていただいたそうですね。
はい。「若手、中堅、ベテラン色々なメンバーがいるので、改めてみんなで共通認識を持つためにやります」という主旨の話を伝えました。「経験のない人は経験を補って、ベテランの人は昨今の考え方に対応できるようにして、共通認識を揃えましょう」と。あとは「じゃあ、やってくださいね」と簡単に伝えただけで、みんな入力を始めてくれました。
実は、始めてみるまでは「やらない人が出るんじゃないか」という不安もあったんです。もし批判的な声が出たら、話し合いをしないといけないな…と身構えていたのですが、そういったこともなく、「みんなでトレニアを始める」という最初の目標地点にたどり着けました。
―日々どのような感じで取り組んでくださっているのですか?
基本的には「自走」してもらっています。現場仕事の人も多いので、みんな別々にやっていますが、それぞれ何か感じてくれているようです。若手の中には知らなかった言葉を書き留めているメンバーもいます。そんな中で、時々話を振ってみると「あ、響いているんだな」という反応が返ってくることもあります。例えば、あるときクイズの解説を読んで「トラブルに巻き込まれたとき、早くリカバリーするためには、いったん「仕方ない」と現実を受け止める。…これってどういうことなんでしょう」と考え込んでいる若手がいました。そのときは「いまのまま続けるのか、いったん離れてみるのか。真逆の考え方ができるのが大事なんだよ」と補足したのですが、普段なかなかこういう話をする機会もないので、トレニアをきっかけに語り合いができました。ベテランの人は、また違う視点で取り組んでくれているようです。パワハラに関するクイズに「立場によって答えが変わるよね」という意見が出たり。ケースバイケースだよね、と捉えつつ、何かしら気づきを得てくれているようです。
― それぞれの立場で取り組んでくださっているんですね。データを見ると、多くの方に「行動や意識の変化」がありますね。
ポジティブに「できた!」とボタンを押す人もいれば、「できている」とは言いづらいと…ストイックな人もいたり。すぐに変化が出ない人もいますが、日々のデータから、「何かしらの変化」が起きているのは感じますね。以前、若手向けに動画研修を取り入れていたときは、1時間の動画を観てもらっても、その後の業務に帰っていったときに、学んだことをどう生かせたのか把握するのが難しかったんですね。また、共通認識を作るために、同じ動画を上司が1時間かけて観るのも現実的ではありませんし。トレニアは、上司も一緒にできるうえに、1人1人からの反応も「ちゃんとやったんだな」「こう考えたんだな」と、毎日、細かいフィードバックが分かりやすい形で返ってきます。費用も手頃で、ちゃんと従業員のためになる、ちょうどいいツールだと感じています。
― 今後、トレニアに期待される効果はどんなところですか?
漠然とですが、本当の意味での「定着」につながるんじゃないかという期待感があります。過去には「他に行っても大変だよ。周りが合わせてくれるわけじゃないよ」と、もったいないなと感じる退職もありました。もし「社会や会社が個人に合わせるべき」という感覚にとらわれてしまうと、どこにいっても満たされず、何より本人がつらいですよね。そうならないためにも、トレニアを通じて、頑張って働ける下地を身に着けて欲しいと思います。
うちの会社は仕事内容も、とくに最初のうちは大変だと思うんです。というのも、スペシャリストではなく、専門性を持ったジェネラリストになることを求めるからです。「ここだけ詳しければ良いですよ」というのは、シンプルで頑張りやすい面はありますが、そうやって作られたスキルは変化に弱かったり、チームワークに支障が出たり、顧客に提供できる価値が狭くなってしまうんですよね。ですから、長期でのキャリア形成を考えると、できるだけ視野は広く持っておいたほうが良いと思っています。最初は特に大変ですが、「全ての事業を分かっている」ところを目指してもらっています。業界ごとの用語、許可事業における法律、さらに土地勘、なかにはマニュアル化しづらい知恵など、膨大な知識と経験が必要になります。それでも、その仕事を見て「楽しそう」と入ってきてくれた人たちを大切にしたい。気長に教えながら、育っていって欲しい。トレニアで学ぶ「社会人基礎力」は、その助けになってくれると思っています。
私自身は、氷河期世代ということもあり、新入社員としての教育を受けた経験がないんですね。マニュアルもない中、働いて、失敗もしながら「そういうものなんだな」と身に着けたことがほとんどです。そうやって身に着けるしかなかったことを、いまトレニアを通じて学べるのは、非常に価値あることだと思います。私も若い頃にトレニアをやりたかったです。
― 本日はお忙しいところありがとうございました。